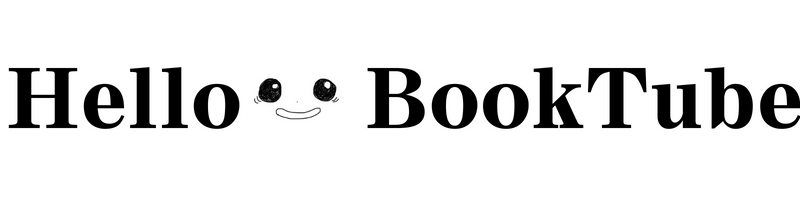海を渡る日本文学シリーズ
少し前の記事で川端康成「雪国」と英訳「Snow Country」の読み比べを公開しました。
日本初ノーベル文学賞として、海外でも多く読まれているのでは?という思いから、読み比べの入り口に選んだのですが、当然海を渡る日本文学は他にもたくさんありますね。
洋書充実!丸善・丸の内で、タトルクラシック(Tuttle)版「Snow Country」を見つけて購入。その時が初めてだったのですが、古典文学の他にも現代作家やビジネス書も多く揃っていました。
海外でも人気の村上春樹氏。「ライ麦畑でつかまえて」の邦訳も手がけているように、自作の英訳にも力を入れているのだろうと推察もするのですが、その他にも色々見かけた現代作家さん。どういう背景で英訳されるに至ったのだろう、とふと思ったりもします。
今回の内容は、タトルクラシック巻末に大量紹介されていた日本文学。
と言います理由は2つ。
①海外で有名な日本文学は読んでおきたい
紹介されているのはやはり古典・名作が多い。読書が好きとはいえ、例えば海外の人から「この間◯◯という作品を読んで、すごく面白かったんだよ」と言われた時に「・・それはまだ読んでいないんだ」という事態を回避したい。全くの想像です、はい。
岩波文庫チャレンジですっかり古典の魅力を実感。今でも優先的に読むようにはしていますが、人類2000年の叡智をすぐさまおさらいできる訳でもなく。“一通り”読み終えたと実感できるまでに、一体どれほどの年月が必要だろうと思ったりもしています。
そんな事もありつつ、本ブログでは、名作を中心に紹介する記事が多い訳ですが、海外で有名な日本文学(古典)という視点で見るのも面白いかなと思いました。
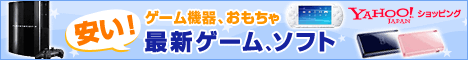
②ヴァージニア・ウルフ的な
「灯台へ」の新訳が新潮文庫から出版されたことが話題となり、読書界隈のSNSで見かけることも多くなりましたが、それ以前であれば、日本ではほとんど名前が挙がらない作家だろうと思ってます。
日頃参考にしている、謂わゆる“読書家おすすめリスト“では、少なくとも私は見かけたことがありません。一方で、このブログで紹介している“好きな作品リスト”には結構な確率でランクインしています。
当ブログが、海外の人を中心に紹介しているからに他ならない訳ですが、特にアメリカではたいそうな人気らしい。大学の教養科目英文学必須リストにも入っているそうです。
ということは、「海外で人気の作家≠日本で有名な作家」なのでは。
であれば、
日本で有名でなくても、海外で人気の作家・作品があるかもしれない。そんなわけで、紹介本を吟味。
ヴァージニア・ウルフの話に戻れば、当ブログで知ってからずっと気になっていた作家でしたので、現在何冊か読み進めている所です。追って記事にできればという所存。
海外で有名な日本文学にもリーチしておきたい、という欲が湧いたところで、タトルクラシック巻末に紹介のある日本文学を中心に、その他海外で有名な日本文学を紹介したいと思います。

タトルクラシック〜巻末メイン
まずはメインで紹介されている作品群。1点ずつ詳細の説明が付いていますが、それぞれ簡略化しています。また全作品をご紹介する訳ではありませんのでご了承ください。
所々自身の感想も挟まりつつですが、お楽しみ頂ければ嬉しいです✨
川端康成
千羽鶴(Thousands Cranes)
「This tale uses Japan’s classical tea ceremony as a backdrop for the relationships between young man Kikuji and two of his late father’s mistresses. Kawabata deftly employs the symbolism of the Japanese tea ceremony as well as the minimalist style of sumi-e, haiku, and Noh theater in this exploration of sex, love guilt, and raw revenge.」
(訳)
物語は、日本の古典的な茶道を背景に、青年菊治と亡き父の愛人二人との関係を描く。川端は、茶道の象徴性、墨絵、俳句、能のミニマリスト的スタイルを巧みに用いて、性、愛の罪悪感、生々しい復讐を探求する。
その他
・伊豆の踊り子(The Izu Dancer and Other Stories)
・古都(The Old Capital)
安部公房
①砂の女(The Woman in the Dunes)
「First published in 1962, this avant-garde work is esteemed as one of the finest Japanese novels of the postwar period, and it was the first of Abe’s novels to be translated into English.
Jumpei, an amateur entomologist on a weekend trip from the city, comes upon a bizarre village among towering dunes where the residents are living deep within pits. Somehow, he is entrapped in the village.
With striking similarities to the work of Franz Kafka, The Woman in the Dunes entices with its unusual plot, its vivid detail, and its existential examination of the human condition.」
(訳)
1962年に出版されたこの前衛的な作品は、戦後日本小説の最高傑作の一つと評価されており、英語に翻訳された彼の最初の小説。昆虫学者の順平が、週末に旅行に出かけ、砂に囲まれた奇妙な村にたどり着く。そこでは住民が穴の奥深くで暮らしていて、ひょんな事にその穴に閉じ込められてしまう。
フランツ・カフカの作品と驚くべき類似点を持つ「砂の女」。珍しいプロット、鮮明なディテール、そして人間の状態に対する実存的な考察に魅了される。
▼ちょっとブレイク▲PART1
実は最近「砂の女」を読みました。そんな訳で少し、自身の感想を挟ませてください(ご興味ない方はすっ飛ばし推奨)。
英訳タイトルは「The Woman in the Dunes」、「砂丘の女」というニュアンス。砂漠に住んでいる女を想像させる。日本語も「砂の女」だから大して変わらない?
いや、自分はこの「砂の女」というタイトルからは、砂の部落の女という意味ではなく、小説で詳しく説明されている「砂」を想像しました。
小説で説明される「砂」
・岩石の砕片の集合体。時として磁鉄鉱、錫石、まれに砂金等を含む。直径2〜⅒mm
・砂の特性は、流体力学に属する問題らしい
・岩石の破砕物中、流体によって最も移動させられやすい大きさの粒子
・絶えざる流動によって、いかなる生物をも、一切うけつけようとしない
・年中しがみついていることばかりを強要しつづける、この現実のうっとうしさ
まとわりつく、うっとうしい女という意味も十分含まれているように思います。現に主人公は、女にまとわりつかれて砂の部落から出られなくなる。
「砂は定着の拒絶」である。はい、一気に安部公房が好きになりました。
安部公房は、最近でこそ盛り上がりを見せている気もしますが、知る人ぞ知る(自分は知りませんでした)、ぐらいの認知度だったのではないでしょうか。
川端康成などと並んで紹介されているのを見て、未だ知らない名作にリーチするという目的に適っている事が分かって、やる気が出た訳✨
②密会(Secret Rendezvous)
「In this surrealistic detective story, a man awakens one morning with the groggy recollection that an ambulance has taken his wife from their home in the middle of the night. In his laborious quest to locate her at the hospital, his senses are assaulted by the depraved environment he enters, a labyrinth filled with odd and insane sights, sounds and people.」
(訳)
このシュールな探偵物語では、ある朝、男がぼんやりとした記憶とともに目を覚ます。夜中に救急車が妻を自宅から運び去ったことを思い出し、病院で妻を必死に探す。途中、奇妙で狂気じみた光景、音、人々で満ちた迷宮のような堕落した環境に足を踏み入れる事になり、奇妙な感覚に襲われる。
三島由紀夫
①宴のあと(After the Banquet)
「Kazu is a successful, independent woman until a former government cabinet minister walks into her life. She marries him even as the wide social and moral gulf between them signals catastrophe.
Kazu has to decide: should she comply with her husband’s strict code of conduct, or return to the independent life she’d once cherished? The climax of this tale reveals Mishima’s full range of power as a master storyteller and novelist.」
(訳)
独立した人生を送っていた女性かづ。元外相の男が現れてから、彼女の生活スタイルに変化が訪れる。社会的にも道徳的にも大きな溝があるにもかかわらず、彼と結婚。
そして彼女は決断を迫られる。夫の厳格な規範に従うべきか、それともかつての自立した生活に戻るべきか。ストーリーテラーであり小説家の名手としての三島の全力が飛び出す。
▼ちょっとブレイク▲PART2
三島由紀夫は海外での知名度も高いと思っていますが、ここで紹介される作品チョイスに痺れました。日本で有名なのは「金閣寺」だと勝手に思っています。自身も少しずつ三島作品を読んでいる所ですが、やはり「金閣寺」が最高結晶のように感じています。
それを差し置いて「宴のあと」とは!
ただこれにも思わず納得。なぜならば「金閣寺」などで炸裂するような三島節は本作にはほとんど出てこないから。
三島節と言って、読んだことのある方には伝わるだろうと思ってます。未読の方へは、なんと言いますか、三島ならではの味や言い回し、つまり難しくてついていけそうもない感じ。
それがない分、非常に読みやすい。三島節のファンには物足りないかもしれない。自身も三島節のファンではありますが、「宴のあと」もかなり好き。節は少ないですが、独特の感性が光る作品だと思っています。
本作は実際の事件が題材。日本で初めてプライバシー権が認められた事件としても有名。三島初読の方や、政治とは選挙とは、を身近に感じる黒教科書のようだとも思っています。
②禁色(Forbidden Colors)
「Widely regarded as Mishima’s finest work, Forbidden Colors explores the issue of sexual hedonism in postwar Japan. An aging, embittered novelist employs the beautiful and young Yuichi Minami to avenge himself on the women who have betrayed him.」
(訳)
三島の傑作として知られる「禁色」。戦後日本における性的快楽主義の問題を探求。老いて憤慨した小説家が、若く美しい南悠一を雇い、自分を裏切った女性たちに復讐していく。
その他
・春の雪(Spring Snow)
・金閣寺(The Temple of the Golden Pavilion)
夏目漱石
①それから(And Then)
「One of Natsume Soseki’s most admired works, And Then is a novel of love and disillusionment that tells the story of a young man for whom idleness has become an expression of rebellion.
Having become thoroughly alienated by the cultural upheaval in Japan, Daisuke has lost the values to guide his life. Yet his refined indifference to everything is completely disrupted when he falls in love with his best friend’s wife.」
(訳)
夏目漱石の最も賞賛される作品の1つであり、怠惰が反抗となった若者の物語を語る、愛と幻滅の小説。日本の文化的激変によって完全に疎外された代助。進むべき道を見失っていたが、親友の妻に恋をし、初めて自分の運命を選ばなければならなくなる。
②こころ(Kokoro)
「Set in the turbulent Meiji era, a chance encounter on a Kamakura beach irrevocably links a young student to a man he simply calls “Sensei.” Intrigued by Sensei’s aloofness and wanting to know more about him, the student calls upon Sensei with increasing frequency.
Sensei draws him back to Tokyo with a letter of heartfelt confession… Written in 1914, Kokoro provides a timeless psychological analysis of one man’s alienation from society, and starkly but gently shows the depth of both friendship and love.」
(訳)
激動の明治時代、青年は、彼がただ「先生」と呼ぶ男性と鎌倉の海岸で偶然出会う。先生のよそよそしさに興味をそそられた学生は、次第に先生を訪ねるようになる。先生は心のこもった告白の手紙で彼を東京に呼び戻し… 。1914年に書かれた「こころ」は、一人の男性が社会から疎外される様子を時代を超えて心理的に分析、友情と愛の深さを厳しくも優しく描いている。
その他
・坊っちゃん(Botchan)
・吾輩は猫である(I Am a Cat)
・草枕(The Three-Cornered World、またはKusamakura)
日本語の教科書、夏目漱石。日本語でも難しい本文がどのように英語になっているのか。非常に興味が出てまいりました。かなりの労力が必要なのでいつになるか分かりませんが、次の読み比べは、尊敬してやまない漱石の作品にしたい。
谷崎潤一郎
①蓼喰ふ虫(Some Prefer Nettles)
「The conflict between traditional and modern Japanese culture is at the heart of this novel. Kaname is a smug, modern man living in a modern marriage. He gamely allows his wife to become the lover of another man, an act that does not cure the profound sadness at the heart of their relationship.
Tanizaki’s characteristic irony, eroticism, and psychological undertones make this novel an exceptional and compelling read.」
(訳)
日本の伝統文化と現代文化の対立。主人公(要)は現代的な結婚生活を送るうぬぼれた現代人。妻が他の男性の愛人になることを認めるが、妻との関係の根底にある深い悲しみを癒すものではなかった。谷崎の特徴的な皮肉、エロティシズム、心理的な含みにより、並外れた魅力的な読み物となっている。
②鍵(The Key)
「In The Key, a middle-aged husband and his wife both seek passion outside of their loveless marriage, telling their stories in the form of parallel diary entries. The novel carefully explores the theme of sexual desire, and Tanizaki’s restrained and delicate prose artfully conveys not only the consequences of the couple’s pursuits, but also demonstrates the very best of Japanese literature.」
(訳)
中年の夫と妻が愛のない結婚生活の外で情熱を求める。物語は日記の形で進行。性欲というテーマを慎重に探求しており、谷崎の抑制された繊細な散文は、夫婦の追求の結果を巧みに伝えるだけでなく、日本文学の真髄をも示している。
その他
・陰影礼賛(In Praise of Shadows)
・細雪(The Makioka Sisters)
タトルクラシック〜巻末その他
これより、作者・タイトルのみの紹介となります(こちらでも一部の抜粋)。
作品と同時に、英語タイトルも見ていると面白い。初めて見る作品や、未読作があればぜひどうぞ✨
芥川龍之介
・河童(Kappa)
・羅生門(Rashomon and the Other Stories)
太宰治
・人間失格(No Longer Human)
ラフカディオ・ハーン
・知られざる日本の面影(Gimpses Of Unfamiliar Japan)
・霊の日本(In Ghosdy Japan)
・心(Kokoro)
・怪談(Kaidan)
井上靖
・風林火山(The Samurai Banner of Furin Kazan)
森鴎外
・雁(The Wild Geese)
永井荷風
・腕くらべ(Geisha in Rivalry)
大江健三郎
・個人的な体験(A Personal Matter)
大岡昇平
・野火(Fires on Plain)
竹山道雄
・ビルマの竪琴(Harp of Burma)
壺井栄
・二十四の瞳(Twenty-Four Eyes)
吉川英治
・新平家物語(The Heike Story)
井原西鶴
・好色五人女(Five Women Who Loved Love)
・世間胸算用(This Scheming World)
紀貫之
・土佐日記(The Tosa Diary)
右大将道綱母
・蜻蛉日記(The Gossamer Years)
紫式部
・源氏物語(The Tale of Genji)
清少納言
・枕草子(The Pillow Book)
吉田兼好
・徒然草(Essays in Idleness)
新渡戸稲造
・武士道(Bushido)
その他
・今昔物語集(Japanese Tales from Times Past)
・百人一首(A Hundred Verses from Old Japan)
・古事記(Kojiki)
・太平記(The Taiheiki)
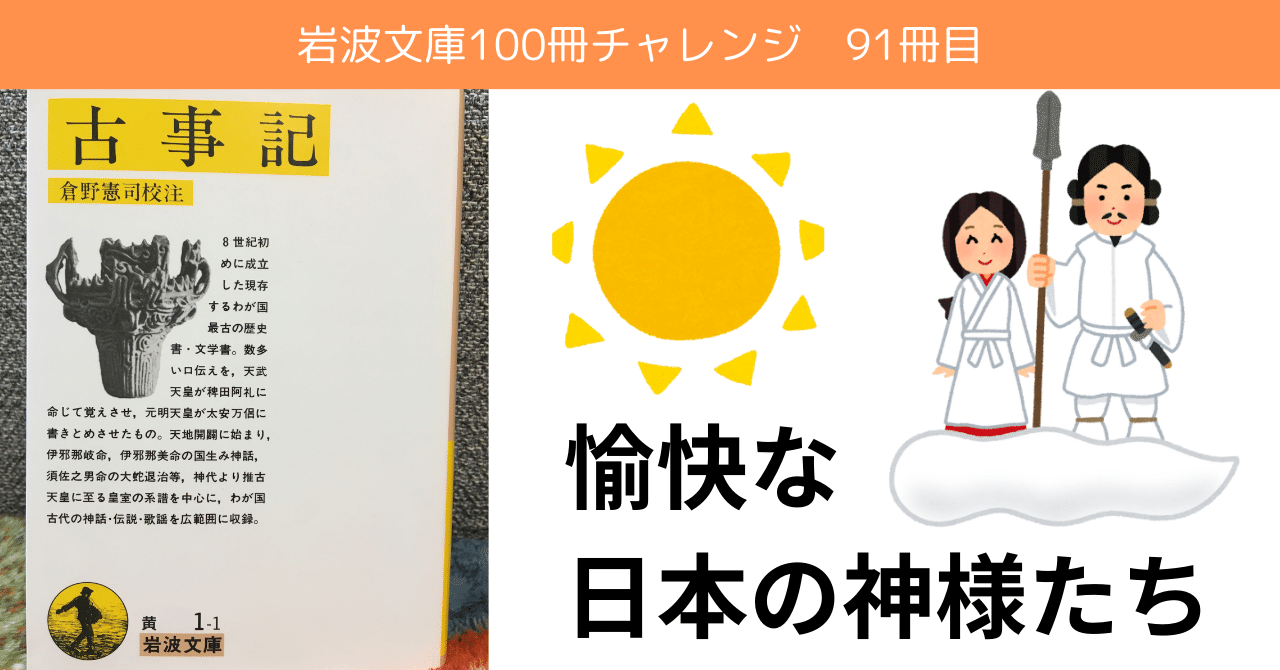
もっと調べてみると
他にも何かあるだろうかと、「アメリカの教科書で紹介されている日本文学」をChatGPTにも聞いてみました。ほとんどが紹介してきた作品と重複しました。以下はその中で重複しなかった数少ない作品です。
・平家物語(The Tale of the Heike)
・古今和歌集(Kokin Wakashū)
・方丈記、鴨長明(Hōjōki)
教科書で紹介される日本文学は、異文化研究の対象。海外で紹介されているザ古典を、どれだけの日本人が実際に読んでいるでしょうか。学校で名前は覚えても作品に親しんだことのない人が大半だと思います。
偉そうなことを言いますが、自身もきちんと読んだことがない。今改めて、1つずつで良いから読み進めていきたいなと、反省をした所です。
【GLOBIS 学び放題】